「提案は“いいね”と言われるのに、最終で他社に流れてしまう」
「打ち合わせを重ねるほど価格勝負に…」。
この悩みは、図面の出来だけでは解けません。鍵はヒアリングの質にあります。初回面談でお客様の暮らし・好み・敷地を一つのストーリーに束ねられれば、そもそもの“比較の土俵”を変えられます。
実際、聞き取りを仕組み化した工務店では、初回プレゼン一発で合意に近づき、商談回数の短縮も実現しています。
本稿では、自社グループのデザインラボを監修していただいている一級建築士の本田先生をお招きして開催された設計セミナーで語られた内容をもとに、明日から現場で使えるヒアリングの5ステップと質問例を、経営者視点で整理します。
なぜ丁寧な聞き取りが、価格競争から抜け出す鍵になるのか?

価格・性能・面積といった要素は、誰でも簡単に比較できる“共通の尺度”です。ですが、これらで勝負しようとすると、必然的に他社との比較が生まれ、価格競争に巻き込まれやすくなります。
そこで重要になるのが、お客様への丁寧な聞き取りです。
お客様がどんな暮らしをしたいのか。その背景にある価値観や、日々の過ごし方まで深く掘り下げることで、「暮らしの物語」が浮かび上がります。この物語は一人ひとりに固有のものであり、他社には真似できない提案の土台になります。
たとえば、「土曜の朝9時、家族がどこで何をしているか?」という問いを通じて見えてくる情景からは、キッチンの配置、収納の量、窓の高さ、照明の種類にまで“理由ある設計”が生まれます。
こうした「理由のある設計」は、無駄な説明を必要とせず、お客様にとっても納得しやすいものになります。その結果、商談回数は減り、初回提案の段階で「この会社に任せたい」という感情的な合意が得られやすくなります。
つまり、丁寧な聞き取りこそが、価格ではなく暮らしそのものを軸にした提案を可能にし、価格競争から抜け出すための大きな武器になるのです。
具体策:本田流ヒアリング5ステップ(実践ガイド)
良いプラン提案は「好み×暮らし×敷地」の交差点にあります。
そこに迷わず辿り着くための近道が、次の本田流ヒアリングの5ステップです。
01
写真共有──好みを“見える化”する
最初の面談で、言葉より先に写真を一緒に見ます。InstagramやPinterestをその場でスクロールしながら、一枚ごとに「どこが好き(または嫌い)か」を部分指定で尋ねていきます。ポイントは、決めつけないこと。お客様がキッチンの写真を保存していても、好きなのは天板ではなく“天井の間接光”かもしれません。
たとえば、外観写真で「この家が好き」と言われたら、「色?素材?開口部の比率?」と軽く仮説を投げ、返答に合わせて深堀りします。「重く見えるから苦手」「抜け感が心地いい」といった言葉が出始めたら、設計者とお客様の“視点”が同期してきたサインです。10分も続ければ、好き・嫌いの地図が見えてきます。
02
テーマ絞り込み──感情を設計指針に変える
次に、その地図を言葉にします。「落ち着く」「余白」「非日常」など、面談で出た抽象語をいったん並べ、三つだけ選びます。ここからが設計者の腕の見せ所。抽象語を具体に“翻訳”するのです。
たとえば「落ち着く」なら、彩度は低め、木目は幅広、照明は面の光中心。「余白」なら、見せる収納1に対し隠す収納3、見切り材は細く。「非日常」なら、どこか一箇所に陰影が生まれる段差を仕込む──といった具合です。三つの言葉は以後の提案の審査員。打ち合わせで迷ったら、「この三語に照らして正しいか」で判断が揃います。
03
ライフスタイル確認──時間で聞くとブレない
面積や部屋数から入ると“普通の間取り”に収束しがちです。そこで、時間軸で暮らしを聞きます。「土曜の朝9時、誰がどこで何を?」から始めると、生活のリズムが自然に語られます。「帰宅から就寝までの流れ」「洗濯・入浴・片付けの順番」「ゴミの一時置きはどこか」など、時系列で辿ることで、家事動線や収納の“根拠”が浮き彫りになります。
ここではできるだけ数値で残しましょう。室内干しの頻度、まとめ買いの量、来客の回数、アウトドア用品の箱数…。たとえば「ファミクロは幅2.0m、掛ける7:畳む3が好み」「玄関土間に一時置き0.5畳と来客靴4足まで」など、後の図面に直結する“生きた数字”がそろいます。数字があると、提案の説得力が一段上がり、商談が短くなります。
04
人となり把握──審美の“源泉”を掴む
住まいの好みは、生活だけでなく価値観からも立ち上がります。好きな映画や音楽、行ってみたいホテルやカフェ、逆に“ダサい”と感じるもの。これらの雑談は単なるアイスブレイクではなく、審美の軸(静/動、直線/曲線、豪華/素朴など)を知るための情報です。
ご夫婦で好みが分かれたら、優先領域を分担すると平和です。たとえば「LDKの最終審査員は奥さま、外観はご主人」。共有部は「素材は無垢、色はグレー、照明は間接」という共通語で整える。こうして衝突を設計に変えると、後戻りがなくなります。面談の空気は軽やかに、「今日は家づくりの恋バナをしましょう」と促すくらいがちょうどいいのです。
05
現地調査──配置の“理由”を身体でつかむ
最後に、敷地そのものと対話します。四隅に立ち、数分間じっと光と風、音と匂いを感じます。隣家の外壁色や屋根勾配、窓の位置を観察し、差別化に使える素材や色のヒントを拾います。交通量や駐車の出し入れを眺めれば、玄関の角度やポーチの奥行きが決まってきます。
変形地ならなおさら、体感がものを言います。三角地の広い辺に庭とLDKを置いて“視線の抜け”を確保する、というような考え方です。現地ではスマホで360°動画と午後の影の位置、周辺の生活音も記録しておくと、社内共有やプレゼン時に配置の理由を説明しやすくなります。
提案はA4一枚で、シンプルに伝える
上記の5つのステップでヒアリングが整ったら、提案をA4一枚程度に要約します。冒頭に「落ち着く/余白/非日常」など三つのテーマワードを置き、次に「土曜の朝9時」など具体的な暮らしのタイムラインを記載。その下に配置図を載せ、光・視線・風の流れは矢印で、収納量や家事動線は数字で示します。最後にコストの見通しとして、選択肢A/Bのパターンを提示します。
プレゼンの冒頭には、下記のような短い“告白文”を添えましょう。
例:「本日のプランは《落ち着く/余白/非日常》の三語をキーワードに、土曜の朝9時が一番ラクになるよう設計しました。」
この一言で、お客様は“私たちのための家”だと腹落ちします。その後の説明では、「だからこの配置です」「根拠はこの数字です」と言い切ることが重要です。「お好みで」「どちらでも」は封印し、意図を明確に伝える姿勢が信頼につながります。
仕組みにすれば、人が変わってもブレない

ここまでの流れは、社内標準として仕組み化しましょう。初回面談のKPIは「写真共有とテーマ(三語)の合意に到達」と定義。月1回のロールプレイを録音して質問や深掘りの質を振り返り、A4一枚のチェックシートで抜け漏れをゼロにします。これだけで「一次プレゼン即合意率の上昇」「打ち合わせ回数の圧縮」「事例投稿の保存率向上」などのプロセス指標が改善し、やがて受注数にも確実に波及します。
重要なのは、属人的な“勘の良さ”ではなく、再現性です。聞き取りが整えば、図面は自然と整います。その結果、工務店 集客の入口で勝てるようになり、価格競争から距離を置く戦い方へ移行できます。
まとめ:図面の前に“暮らし”を設計する

今回ご紹介した「本田流ヒアリングの5ステップ」――
- 写真共有 → 好みを可視化
- テーマ絞り込み → 指針を3語に集約
- ライフスタイル確認 → 時系列で家事・収納を把握
- 人となり把握 → 価値観の源泉を言語化
- 現地調査 → 配置の“理由”を体感で掴む
先に“暮らしの設計”を終えてから図面を引くことで、初回プレゼンの説得力が一段上がり、価格比較のゲームから自然に降りられます。この順序を社内標準にすれば担当が替わっても品質は安定し、工務店 集客の歩留まり(面談→設計契約)も改善します。
標準化こそ、最強の差別化。 聞き取りに根拠ある線を重ね、地域で“比べられない工務店”になりましょう。
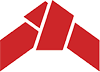
この記事で「うちでも試したい」と思われた方へ
まずはA4一枚のヒアリング雛形から始めませんか。
初回無料のZoom相談で運用のポイントをご紹介します。
お気軽にお問い合わせください。


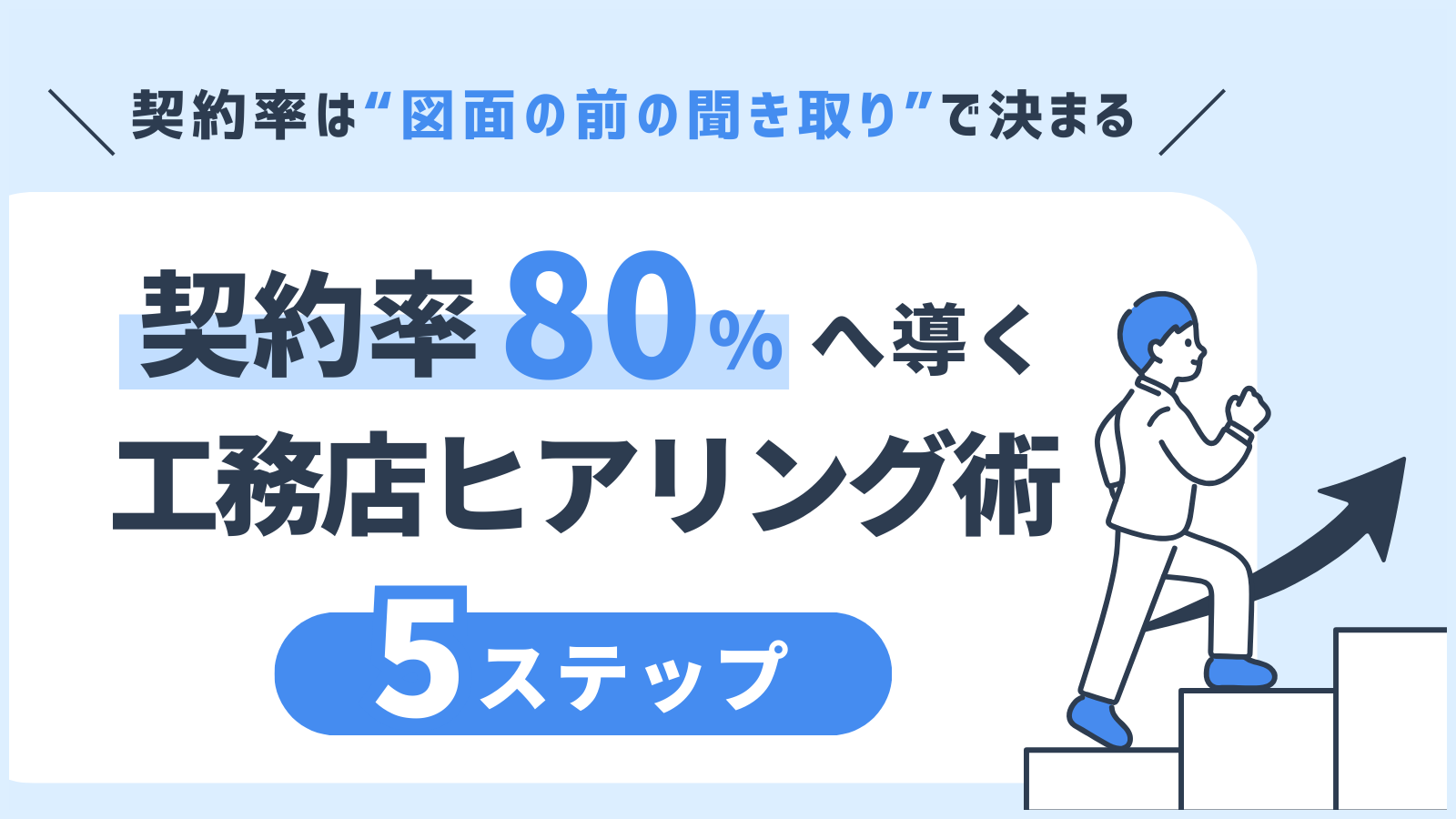





 059-340-0244
059-340-0244